例外を許し続けたら、仕組みは音を立てて崩れた。
「今回だけ」のはずが、いつの間にか“毎回”になっていた。
元社長の私は、不介入の仕組みを作った後も、「例外」だけは自分が判断していいと思い込んでいた。気づけば現場は迷子になり、数字も機能せず、責任の所在は再び不明確に。崩壊の引き金は、私自身だった。
この記事では、仕組みが崩れた経緯と、立て直しのために実行した具体策を共有する。
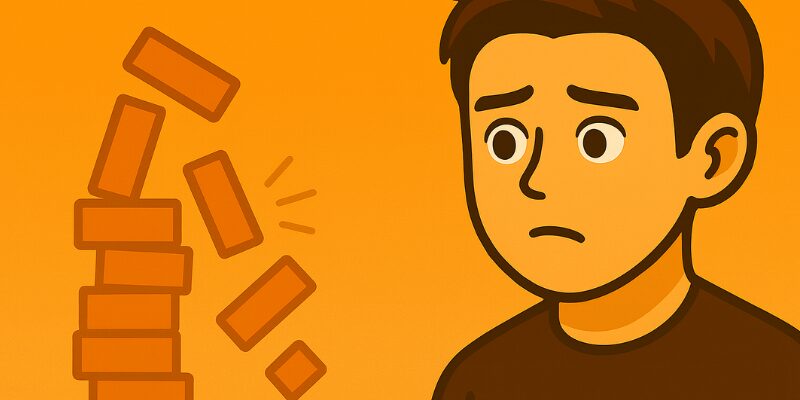
こんな人に読んでほしい
- 「今回だけ」を繰り返してしまう経営者・管理職
- 現場の自主性と統制のバランスに悩んでいるリーダー
- 崩れた運用を立て直したい人
この記事で伝えたいこと
- 例外を管理する仕組みの重要性
- 仕組み崩壊のサインを見逃さない視点
- 立て直しのための即効性ある手順
1. 崩壊の始まりは「例外だからOK」から
数字とルールで現場任せの運用をしていた頃、想定外の案件が発生。私は「これは特別だから」と介入した。その場は助かったが、それ以降「今回も特別扱いで」と現場が判断を委ねるようになった。例外が積み重なり、ルールが形骸化していった。
2. 崩壊を止めるために決めた“例外処理のルール”
私は次の3つを設定した。
①例外は事前登録制:Slackに専用チャンネルを作り、発生理由と期限を記録。
②期限切れ自動リセット:期限を過ぎたら元のルールに戻す。
③月次レビュー:例外の発生回数と原因を共有し、再発防止策を立てる。
この仕組みで、例外は一時的なものに戻り、ルールの信頼性を回復できた。
3. 崩れた仕組みを立て直すときの心構え
一度崩れたルールは、再構築に時間がかかる。だからこそ、私は「スピードよりも透明性」を優先した。何を変えたのか、なぜ戻すのかを全員に説明し、納得感を作ることを最優先にした。これにより、現場は再び自分たちで判断できる空気を取り戻した。
まとめ
- 例外は“仕組みの外”に置き、期限と記録をセットで管理する
- 崩壊のサインは「例外が常態化」したときに出る
- 立て直しには透明性と納得感が欠かせない
次回予告
vol.32『数字が裏切った日——指標に頼りすぎた私の失敗』
順調に見えた数字が、実は現場の実態を隠していた。元社長として、なぜ数字を盲信したのか、そこから学んだ指標の使い方を語ります。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします


