棚の奥の“失敗フォルダ”が、いちばん強い武器になった。
「あの時のメモが、今日の受注を連れてきた。」
資金繰りに追われていた頃、新規の扉は重く、提案も空回りした。そんな時に頼ったのは、過去の提案書、失注理由、クレーム対応の記録——当時は恥ずかしくて見返したくなかった“黒歴史”だった。
営業が停滞したときこそ、過去の自分を資産化する。私はその遅すぎる学びで、商談の再現性を取り戻した。
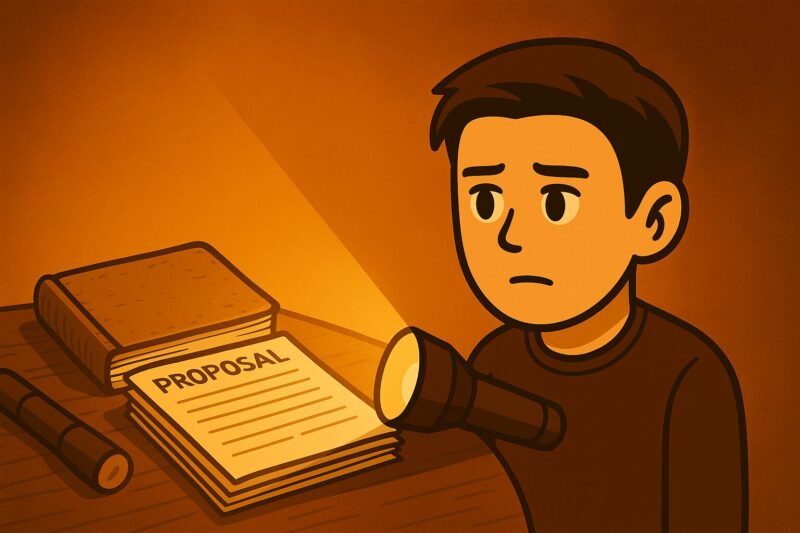
こんな人に読んでほしい
- 新規開拓が伸びず「何を直せば良いか」霧の中にいる経営者
- 提案の質が属人化しており、再現性に悩む営業責任者
- 失注分析が形骸化し、会議が blame で終わりがちなチームのリーダー
この記事で伝えたいこと
- 過去資産(失敗・成功・素材)を“探しやすく・使いやすく”する視点の大切さ
- 自分自身と向き合い、痛い記録を言語化してナレッジ化する方法
- 明日の提案を変える最小の一歩(テンプレ化と再利用設計)
1. 倉庫のダンボールから始まった逆転
社長だった私は、新規が落ちた原因を「マーケットが悪い」で片づけた。だが、古い失注メモをめくると、
価格ではなく“導入後の不安”が一貫していた。にもかかわらず、提案書は機能比較が9割。
過去の自分が残した赤字コメント——「社内展開の段取りが見えない」「KPIの責任の所在不明」——を拾い、
リスク先回りの1枚資料を新たに冒頭へ差し込んだ。結果、次の商談で初めて「値引きなし」で前に進んだ。
2. 棚卸しの型:3つのフォルダで再現性を作る
過去資産は「記憶」ではなく「検索」できる形にする。私がやり直したのはこの3つ。
- ①失注図鑑:案件名/業種/失注理由(顕在・潜在)/言質引用/対策案を1カードに。
タグは「社内合意」「運用負担」「優先度競合」「キーマン不在」などに統一。 - ②成功プレイブック:勝ち筋を“問い”で残す。「導入後の初週タスクは誰が?」など、会話の順序まで記録。
- ③素材ライブラリ:図表・事例・FAQをスライド単位で保管。提案書は“組み立てるもの”に変える。
失敗談を晒すのは痛いが、現場は“リアルな弱点”を欲している。経営会議で私が先に自分の失敗カードを出すと、チームの投稿量が3倍になった。
3. それでも前に進む理由
過去は変えられないが、過去の自分は味方にできる。棚卸しを続けると、提案の初速が上がり、属人差が縮まる。
「今日はダメだった」が、「明日は同じミスをしない」に変わる瞬間——それが再出発の実感だった。
まとめ
- 失注の大半は“言いにくい不安”——カード化して見える化
- 勝ち筋は“問い”でテンプレ化、素材はスライド単位で再利用
- 経営者がまず自分の失敗を開示すると、ナレッジは循環する
次回予告
vol.21『やさしさの使い方を、少しだけ変えてみた』
次回は、甘さと優しさの境界線。顧客・部下・自分に向ける“やさしさ”を営業設計にどう反映させたかを語ります。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします


