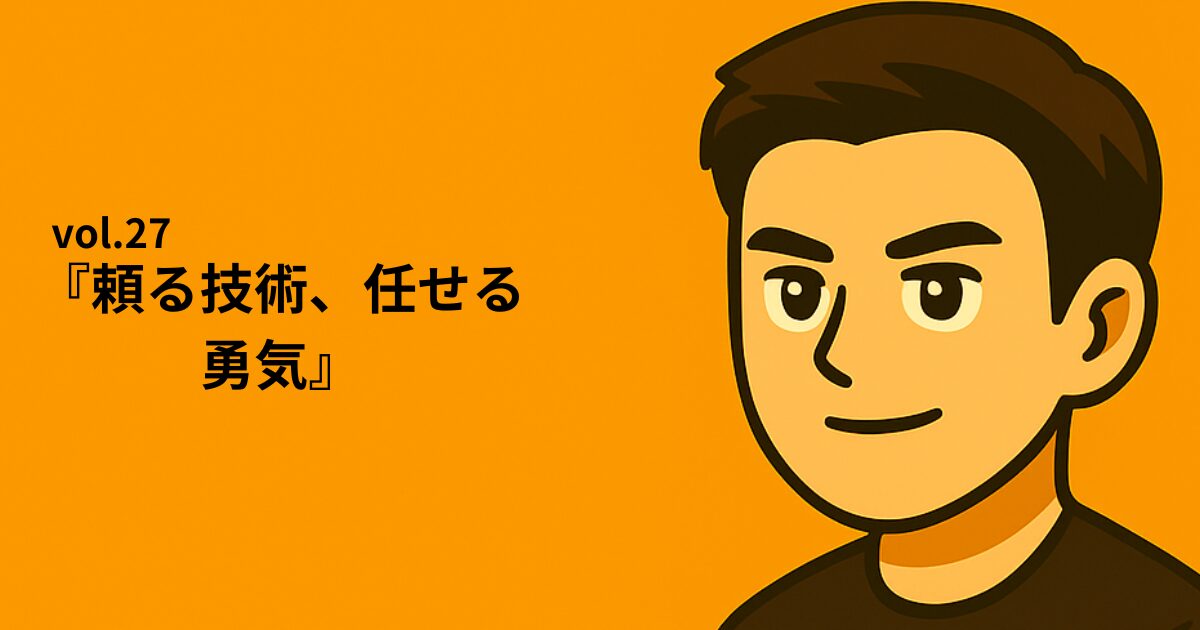「自分でやる」が最速だったのは、昨日まで。
任せたつもりで抱え込み、チームの成長も売上も止めたのは私だった。
「品質は自分が一番わかっている」という慢心で、見積もり作成から提案レビュー、クロージングまで私の机に渋滞。気付けば、商談は“社長待ち”。スピードは鈍り、現場の判断力は育たなかった。
任せ方を変えたら、初めて売上と主体性が同時に伸びた。

こんな人に読んでほしい
- 「結局、最後は自分がやる」に戻ってしまう経営者・営業責任者
- 部下に任せても成果がズレ、手戻りで疲弊している人
- 属人営業からチーム営業へ移行したいが、具体策が見えない人
この記事で伝えたいこと
- 「任せる」は作業移管ではなく、意思決定の委譲という視点の大切さ
- 任せ方の設計(権限・判断基準・レビュー頻度)の具体
- 再出発のための一歩——委譲で生まれる営業スピードと再現性
1. 失敗した“丸投げ”と“抱え込み”の両極
元社長の私は、忙しさに負けて二択を繰り返した。
・丸投げ:目的も判断基準も伝えず依頼→提案が迷子、手戻り地獄。
・抱え込み:全部自分で修正→現場は“待つ習慣”だけが定着。
どちらも売上の最大ボトルネックは「社長の手」の空き具合になった。案件は溜まり、決裁は遅れ、競合に先着される。原因は「任せる設計」を怠ったことだった。
2. 任せる技術——3つの枠で権限を可視化する
私がやり直したのは、案件ごとに権限と基準を“1枚”で定義すること。
【委譲キャンバス(A4)】
①目的:この商談で何を証明するか(例:3ヶ月でLTV回収見込みを検証)
②判断基準:価格・納期・機能のトレードオフの許容幅(例:価格±5%、納期最短優先、機能はMVP)
③指標:意思決定の拠り所(例:粗利率30%以上/商談リードタイム10営業日以内)
④権限:誰がどこまで即断できるか(例:割引5%までは担当判断、超過はマネ判、例外は週次会議)
⑤レビュー頻度:初回提案前とクロージング前の2回のみ。途中はSlackで要点報告。
⑥失敗の安全網:失注理由テンプレと学び共有の期限(24時間以内)。
これを運用してから、商談の停滞理由が「確認待ち」から「顧客課題の深掘り」に変わり、会議は“報告会”から“意思決定の場”になった。
3. それでも前に進む理由
任せると品質が落ちる恐怖は消えない。だからこそ、品質を守るのは「人」ではなく「基準」と「仕組み」にする。基準があれば、失敗は局所化され、学びは全社化できる。私が勇気を持てたのは、任せた週に商談サイクルが短くなり、受注の“勝ちパターン”がチームの言葉で語られ始めたからだ。経営者が手放した分だけ、営業は前に進む。
まとめ
- 丸投げでも抱え込みでもなく、「判断基準ごと委譲」する
- A4一枚の委譲キャンバスで、権限・指標・安全網を明文化
- レビューは回数より質。節目2回でスピードと再現性を両立
次回予告
vol.28『任せたことで芽生えたチームの主体性』
次回は、委譲後に現場が自走し始めた具体的な変化。KPIの持ち方、会議の主導権、成功事例の水平展開の“つまずきと修正”をお届けします。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします