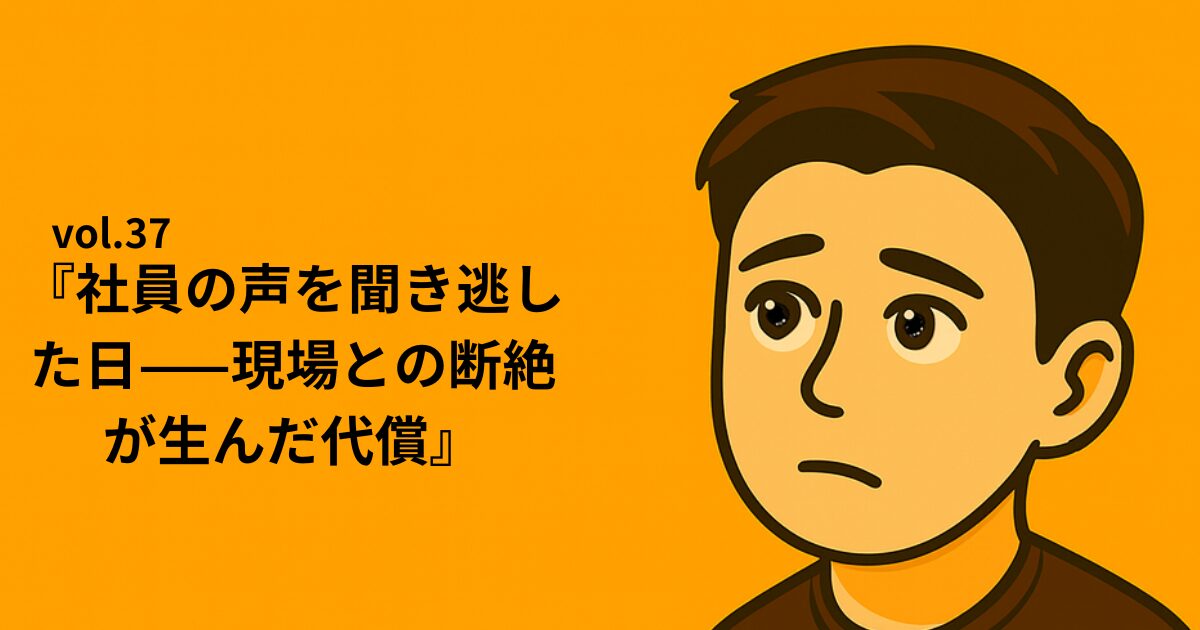現場の一言を無視した瞬間、営業は数字だけの“作業”になった。
「今の提案、刺さってません」——若手のつぶやきを、私は聞かなかった。
元社長として、私は会議室のKPIを信じすぎ、顧客の生の反応を持ち帰る現場の声を軽く扱っていた。結果、机上の戦略と顧客の痛みはズレ続け、契約は直前で失注が増えた。
この記事では、経営者としての営業課題——価格・商談設計・顧客選定・レビュー運用——で私がやらかした失敗と、現場と経営を再接続した具体策を記す。

こんな人に読んでほしい
- 「会議では前向き」なのに商談現場で失注が続く経営者・営業責任者
- 価格と価値訴求のズレに違和感を覚えているが修正できないリーダー
- 現場の声を定性で集めているのに、意思決定へ反映できていない人
この記事で伝えたいこと
- 経営者の営業課題で起きがちな「断絶」の正体
- 失敗を繰り返さないための、声→設計→意思決定の反映サイクル
- 現場と経営をつなぐ、週次の最小仕組み(テンプレ付)
1. 私が犯した4つの営業ミス
①顧客選定(ICP)の過信:スライド上の理想顧客像に固執。現場は「決裁スピードが遅い層」に時間を溶かしていた。
②価格の“根拠なき強気”:原価+目標粗利で逆算。顧客の節約対象リスト(Budget Kill List)に入っている事実を無視。
③商談の型崩れ:製品デモ先行で、痛み(Pain)の言語化が浅いまま比較検討に入って失速。
④レビューの虚無化:パイプライン数字の羅列だけで、「なぜ勝ち、なぜ負けたか」の学習がゼロ。
2. 現場の声を“意思決定”に変える最小サイクル
①週次VoC(Voice of Customer)メモ:各商談で出た原文の痛みを3行で記録(発話者・状況・正確な言い回し)。
②勝ち負けタグ:案件ごとに #価格 #導入負荷 #競合機能 #意思決定者不在 など固定タグを必ず付与。
③10分レビューフレーム(軽量MEDDICC):
- Metrics(数値的ゴール)/ Economic buyer(誰が財布を持つか)
- Decision(プロセス)/ Pain(痛みの言語化)
- Compete(競合の立ち位置)/ Next step(日時まで)
④価格のA/B根拠:割引率・障害要因・導入負荷の相関を2週間に一度だけ確認。感覚での強気/弱気を禁止。
⑤経営の宿題化:VoCから経営が決めるべき論点(対象市場の微修正、プラン廃止、初期費用の再設計)を毎週1つだけ決裁。
3. それでも前に進む理由
現場の声は、時に不都合だ。戦略スライドを壊すからだ。だが、壊れるのはスライドであって、事業ではない。
私は商談同席を月2回に増やし、「決裁者の沈黙」や「導入後の運用者の不安」を自分の耳で拾うようにした。それだけで、提案書の順番、価格の説明、比較表の作り方が変わり、失注理由が“憶測”から“事実”に置き換わった。
まとめ
- 数字だけの会議は学習しない。現場の原文VoCを経営の議題へ
- 勝敗タグと軽量MEDDICCで、商談を“再現可能”にする
- 価格は気合でなく根拠で動かす——相関を見て決める
次回予告
vol.38『価格で殴って失った信頼——値引きの副作用と立て直し』
短期受注のための値引きが、長期の信頼を削った。価格戦略のやり直しと、現場説明の再設計について語る。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします