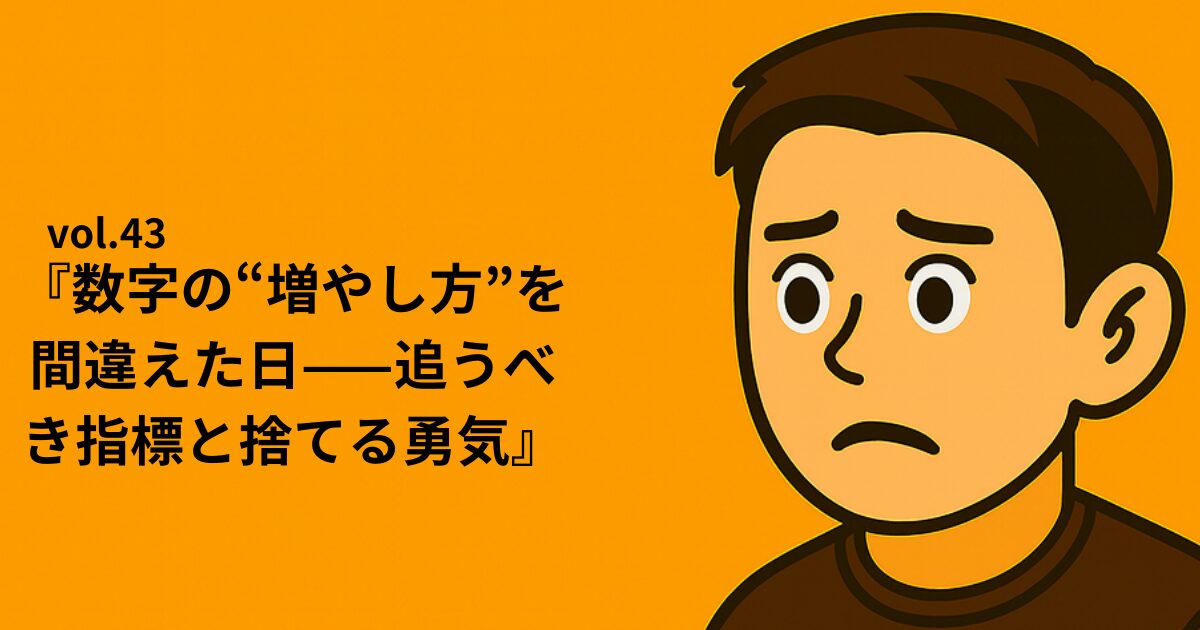数字は増えた、でも売上は増えなかった。
「KPIは全部“達成”なのに、なぜ利益が出ないのか?」
私は数字を“増やす”ことに必死で、増やしてはいけない数字まで膨らませていた。
架電数、訪問数、商談数——追いやすい指標ばかりがダッシュボードを埋め、
顧客が動くための“質”は置き去りになっていた。この日を境に、私は“捨てる指標”を決めた。

こんな人に読んでほしい
- KPIは達成しているのに収益が伸びない経営者
- 営業活動が「量先行」になっていると感じるマネジメント
- 指標設計を見直したいけれど何を捨てるべきか迷っている人
この記事で伝えたいこと
- “追いやすい数”と“成果につながる数”の切り分け方
- KPIからKQI(価値指標)への置き換えと運用設計
- やめる指標・減らす活動を先に決める意思決定のコツ
1. 増やしたのは活動量、削ったのは商談の深さ
私は「活動が増えれば成果が出る」と信じ、電話・メール・訪問の件数にノルマを課した。
現場は数字を満たすため、温度が低い見込みにも時間を使い、結果として本当に進む商談の時間が削られた。
失注理由の多くは「課題深掘り不足」「意思決定者との接点なし」。
私が増やしたのは“数えるのが簡単な数字”で、売上に響く接点の質ではなかった。
2. 捨てたKPI/残したKPI/新しく設計したKQI
ダッシュボードを棚卸しし、次のように再設計した。
■ 捨てたKPI:総架電数・一斉メール送信数(量は閾値のみ管理)
■ 残したKPI:初回面談数、提案提出数、次回確約率(ネクストがある行動)
■ 新KQI(Quality):
・仮説一致率(ヒアリングで想定課題が実在した割合)
・意思決定者同席率(商談に決裁者が入った割合)
・提案再現率(次の顧客にも使える学びが提案に反映された割合)
追えば増える数字を減らし、追わないと鈍る“質”を採用した。
3. 運用で変わったのは「会議」と「時間の使い方」
週次会議は“報告”をやめ、検証スプリントに変更。
①先週の仮説→②実行ログ→③結果→④学び→⑤スクリプト更新、を各自5分で回す。
また、温度の低い案件を早く捨てるルールを徹底。見込みの“除外”を称賛する文化を作った。
結果、面談数は微減したが、次回確約率と平均受注単価が上がり、粗利が回復した。
まとめ
- 増やすべきは“量”ではなく“前進の確率”
- KPIは少なく、KQIで深さを担保する
- やめる指標を先に決めると、時間が利益に変わる
次回予告
vol.44『会議が増えたのに成果が出ない——議題設計と意思決定のやり直し』
次回は、会議体を増やしても現場が動かなかった原因と、意思決定を前に進める“議題の作り方”を失敗談込みで共有します。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします