「要望」を聞いたつもりが、「前提」を聞けていなかった。
言葉は合っていた。意味がズレていた。
「導入は急いでいない」という一言を、私は“見込み薄”と決めつけて引いた。
実際は社内稟議の段取り待ちで、こちらが伴走すべきタイミングだった。耳で聞くのではなく、業務の文脈と意思決定プロセスまで聴けていたか。営業を率いる経営者としての痛恨のミスを記す。
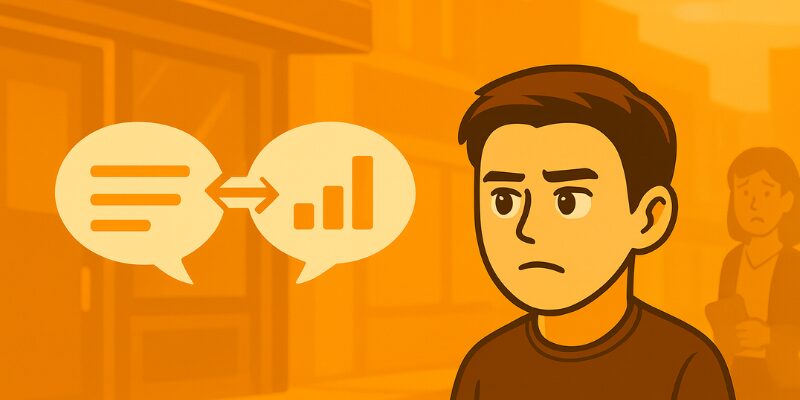
こんな人に読んでほしい
- ヒアリングしたのに提案が刺さらないと感じている経営者・営業責任者
- 商談の温度感を読み違えて機会を逃しがちな人
- 顧客の意思決定プロセスまで含めて設計したい人
この記事で伝えたいこと
- “表面の要望”と“本質的なニーズ(仕事の因果)”の区別
- 意思決定プロセス(誰が・いつ・どう決める)の聴取が提案精度を左右する
- 仮説→検証→要件再定義→合意という最低限の営業設計
1. 失敗:言葉どおり受け取り、機会を自ら手放した
ある中堅企業のDX案件。担当者は「比較検討中で、導入は急いでいない」と発言。
私は“今は動かない顧客”と解釈し、追客頻度を落とした。数週間後、競合が受注。
後から聞けば、意思決定者は別におり、稟議資料づくりの伴走を求めていた。
私は「ニーズ」を聞いたつもりで、意思決定の段取りニーズを聞けていなかった。
2. 学び:ヒアリングの設計を“仕事の因果”で組み立てる
以降、質問は次の順に固定した。
①現状業務の因果(どの業務/誰が/何が詰まって損しているか)
②理想状態の定義(何が見えれば意思決定できるか、成果指標は何か)
③意思決定プロセス(関与者・予算・期限・稟議フォーマット)
④不採用条件(導入しない理由は何か、何が欠けたら見送りか)
これで、表面的な“機能要望”ではなく、提案が通る経路まで把握できるようになった。
3. やり直し:提案は“資料”ではなく“合意形成の段取り”
提案の中身も変更。
・機能説明中心 → 意思決定者向け1枚サマリ+稟議に使える効果試算
・納期/価格提示 → 導入後90日のKPI・レビュー日程・役割表
・質疑応答の場 → 異議リストを先出しし、反証データで潰す
結果、担当者が社内で説明しやすくなり、受注率と決定スピードが改善した。
まとめ
- 言葉どおりの要望は“素材”。意思決定の段取りまで聴いて“設計図”にする
- ヒアリングは「機能」より「因果・指標・プロセス」
- 提案は“説明”ではなく“社内合意形成の支援”
次回予告
vol.46『提案が通らない日——キーマン不在で起きた商談迷子』
次回は、決裁者不在のまま商談を進めて迷走した失敗談と、関与者マップの作り方・巻き込み方の実践を書きます。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします


