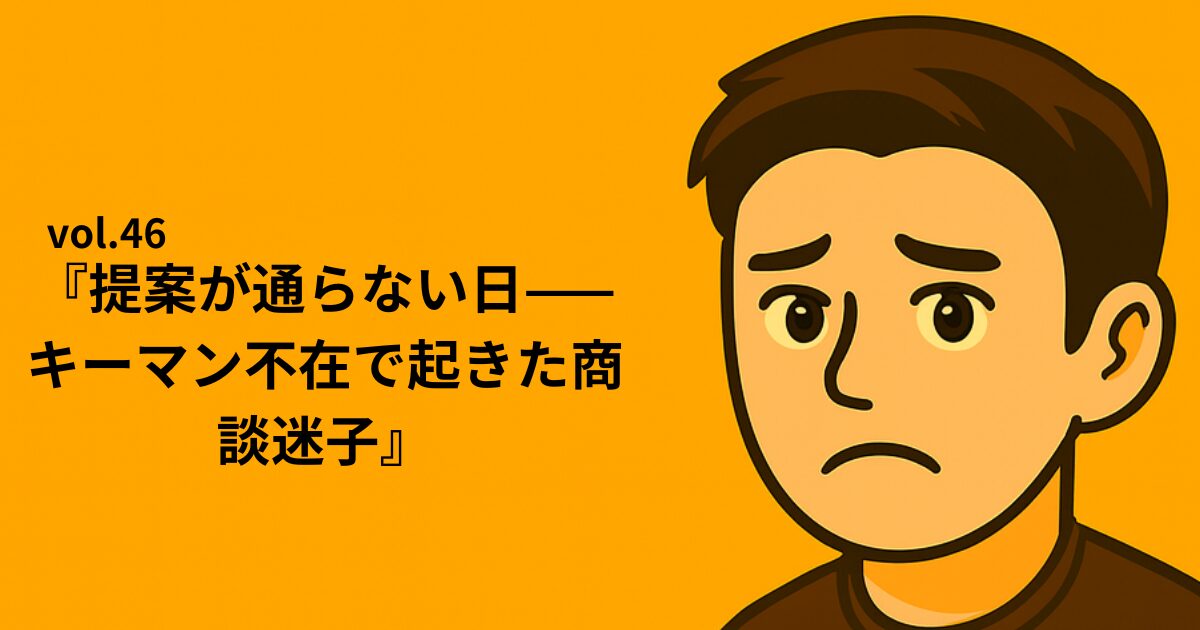「いいですね」は賛成ではない。決める人に届かなければ、提案は存在しない。
担当者の好感触に安心した私が、いちばん肝心な“決裁動線”を見落とした。
会議体・影響力・社内政治。誰が決め、誰が止めるのか——訊かずに進めた提案は、社内で迷子になって消えた。
元社長としての営業設計の欠陥と、やり直しの具体策を記す。
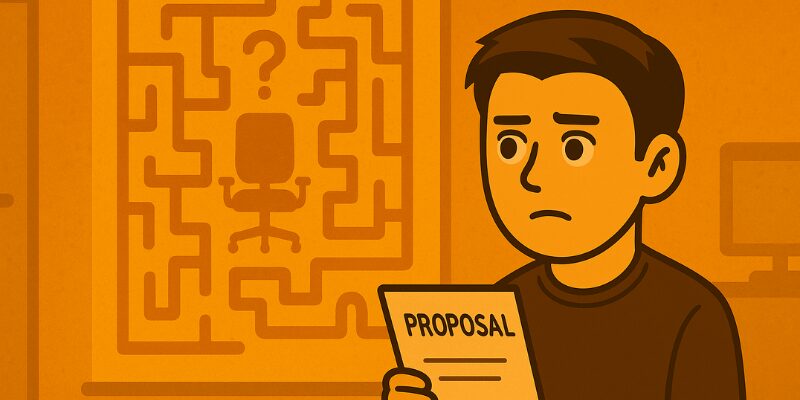
こんな人に読んでほしい
- 担当者とは盛り上がるのに、社内決裁で落ちる案件が多い経営者・営業責任者
- デモ後に音信不通になりがちで、原因が特定できていないチーム
- 決裁者に会えないまま見積・提案書を出してしまう文化を変えたい人
この記事で伝えたいこと
- “好感触”と“合意”は別物——キーマン定義とアクセス条件が先
- 会議体・稟議・反対勢力を可視化する関与者マップの作り方
- 決裁者に会えない時の代理合意パッケージ(1枚資料・効果試算・反論つぶし)の運用
1. 失敗:担当者の「前向き」を“社内合意”と取り違えた
SaaS導入案件。窓口の課長は強く共感し、PoCも好調。私は「いける」と判断し、
価格交渉に応じて提案書を提出。しかし、最終会議で役員が初見となり、「今やる理由が弱い」の一言で白紙化。
反省点は明確だった。私は早期に決裁者(役員)・CFO・情報システムの参加条件を取りに行かなかった。
2. 学び:関与者マップと“会える条件”を先に取りに行く
以降、最初の打合せで次を必ず確認した。
・意思決定者は誰か/最終会議はいつか
・関与者ごとの関心(経営:収益性、現場:運用負荷、情シス:セキュリティ、財務:ROI・減価)
・不採用条件(今はやらない理由、競合の強み、社内障害)
そして、キーマンに会える条件を合意できなければ、PoCも値引きもしない“ルール”を徹底した。
3. やり直し:決裁者に届く“代理合意パッケージ”を標準化
どうしても会えない時は、担当者が社内で戦える武器をセットにした。
・1枚サマリ:課題→効果→費用→90日KPI→体制の図解
・効果試算:既存業務の時間単価×削減時間=粗利改善の試算表(前提条件付き)
・反論FAQ:「今じゃなくていい」「セキュリティは?」など役員想定質問への回答テンプレ
・導入ロードマップ:週次マイルストーンとリスク箇所、責任分担表
これで「届く」確率が上がり、意思決定のスピードも改善した。
まとめ
- 担当者の好感触=受注見込み、ではない。決裁者に会える条件を先に取る
- 関与者マップで“誰が決め、誰が止めるか”を可視化する
- 会えない時は、1枚サマリ+効果試算+反論FAQで代理合意を設計する
次回予告
vol.47『値引きでしか動けなくなった日——価値訴求の立て直し』
次回は、ディスカウント依存で粗利とブランドを削った失敗と、価値の再定義・比較の設計で巻き返した話を書きます。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします