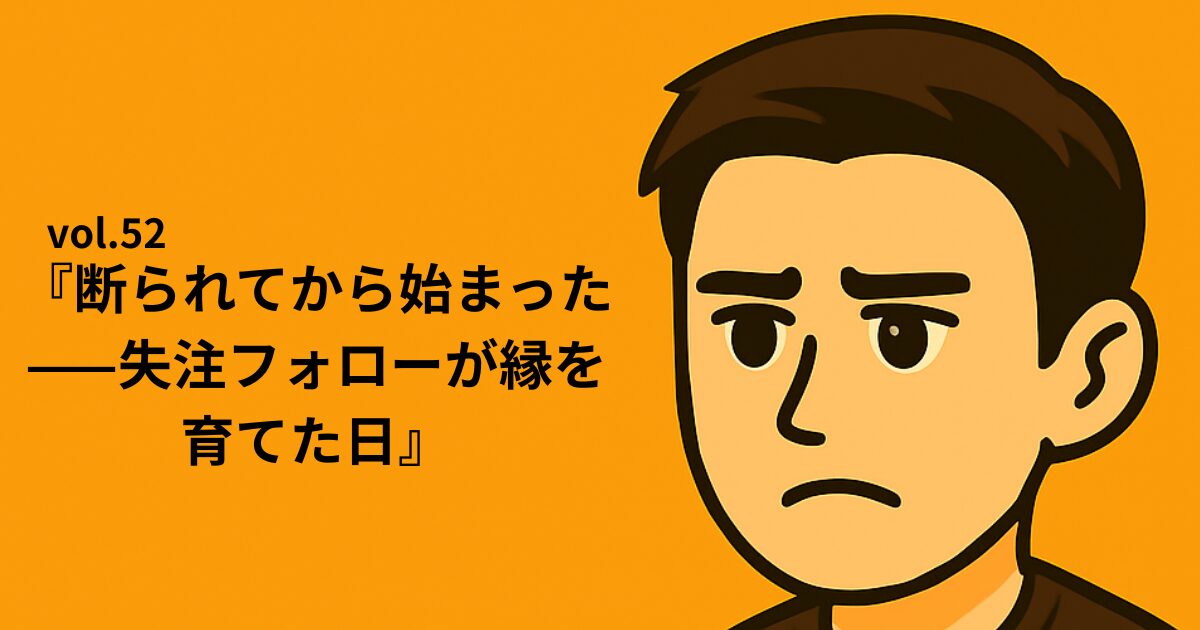終わりに見えた瞬間が、本当のスタートだった。
「今回は見送ります」——それでも私はメールを閉じなかった。
元社長として、失注は“敗北”だと決めつけていた。悔しさを飲み込み、次の商談へ逃げるのが常だった。しかし一度だけ、理由をきちんと聴き、価値を置き土産にして帰った日がある。数か月後、その企業から指名で連絡が来た。
失注後の行動が、受注前の信頼をつくる。私はそこで営業をやり直した。

こんな人に読んでほしい
- 失注後のフォローが形骸化しており、縁が途切れがちな経営者・営業責任者
- 検討は盛り上がるのに最終で負ける、競合比較で後塵を拝している人
- 短期成果に追われ、関係資産(将来受注・紹介)を積めていないと感じている人
この記事で伝えたいこと
- 失注は「次の意思決定の設計」に変えられるという視点
- 関係を切らない3点セット(感謝・学び・価値の置き土産)
- 再接点を生む具体的な運用(CRMルールと90日後の動線)
1. 「断られた後」にやったことで変わったこと
あの日、私は即返信で反射的に礼だけを送らなかった。
代わりに、三行失注メールを自分ルールにした。
1行目:感謝「丁寧なご検討とコメント、心から感謝します。」
2行目:学び「今回の決定理由(例:導入タイミング・社内合意)が当社の提案改善点でした。」
3行目:置き土産「同じ論点で役立つチェックリストを添付します。社内共有にご自由にお使いください。」
さらに5分の電話をお願いし、意思決定プロセスのどこで負けたかだけをヒアリング(機能比較は聞かない)。そこで“決裁者が求めた社内説得素材の不足”を知り、次の提案から「1枚の社内説明用スライド」を必ず付けた。
結果、同業他社の別部門から紹介が来た。最初の案件は落としても、組織の中に味方ができた。
2. 比べないことで見えた「相手の成功定義」
失注直後は、つい競合と自社を細部で比べたくなる。しかし相手が比べていたのは“ベンダー間の優劣”ではなく、「社内で通せるかどうか」だった。
そこで私は、フォローを“自社の正しさの主張”から“相手の社内合意の支援”へ切り替えた。送るのはパンフではなく、相手社内の反対論点に先回りしたテンプレ:
・投資対効果の算定シート(前提条件つき)
・リスクと対策の1枚表(導入/運用/セキュリティ)
・段階導入プラン(スモールスタートの工程表)
これらは競合比較ではなく、意思決定を前に進める“社内用ツール”。比べないことで、相手の成功定義がやっと見えた。
3. それでも前に進む理由
失注フォローは短期の数字にならない。だからこそ、仕組みにした。
・CRMで失注理由を「表層(価格/機能)」「構造(決裁/予算期)」「タイミング」に分けて選択必須。
・理由が「構造/タイミング」の案件は90日後リマインドを自動付与、メール雛形は“近況質問+小さな価値提供”で固定。
・月次会議で「受注件数」だけでなく失注後の再接点率を営業KPIに追加。
こうして、断られた後に積み上がる“関係資産”をチームの成果として可視化した。私が続けられたのは、数字が「縁づくり」をちゃんと評価してくれたからだ。
まとめ
- 失注は終わりではなく、意思決定を設計し直す合図
- 感謝・学び・置き土産の三行で関係を切らない
- “社内合意の支援物”を渡すと、再接点が生まれる
- CRMとKPIで「縁づくり」を仕組み化する
次回予告
vol.53『紹介が止まった日——頼み方を変えたら再び回り始めた』
次回は、紹介依頼が空回りしていた頃の失敗談と、読者の皆さんにも使える“紹介が生まれる伝え方・タイミング・一言テンプレ”を、元社長の実例付きでお届けします。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします