⏱ 読了目安:約3分
「決めない会議」を、15分で「決める場」に変える。
結論から言う。——会議は長いから遅いのではない。最初の30秒で“何を決めるか”が決まっていないから遅い。
元社長時代、2時間の会議で何も決まらずに解散。翌週また集まり、さらにすれ違う——そんな悪循環を何度も見てきた。ある日、私は15分アジェンダを導入した。最初の30秒で目的と決裁単位を言い切る。結果、会議は「情報共有の場」から「意思決定の装置」へ変わった。
今日はその設計と、明日から使える“冒頭スクリプト”を置いていく。
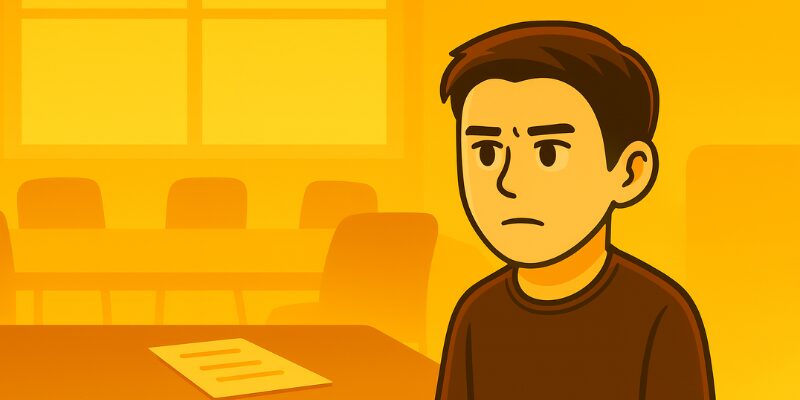
こんな人に読んでほしい
- 会議後に「で、何が決まったの?」が口癖になっている経営者・リーダー
- 資料が多すぎて議論が散らばるチーム
- 合意形成に時間をかけず、実行を早めたい人
この記事で伝えたいこと
- 決裁を早くするのは“時間短縮”ではなく“単位の明確化”だという視点
- 15分アジェンダ(5項目×3分)の実装方法
- 明日から使える冒頭30秒・締め60秒の台本
1. 決裁が遅い原因と、15分アジェンダで変わったこと
私が見てきた遅延の正体は、①目的の多重化、②決裁単位の不明確、③判断材料の出し惜しみ。
そこで会議を“15分×1テーマ”に分解し、下記の順番を固定した。
15分アジェンダ(3分×5つ)
1) 目的:この15分で何を決める?(例:A/Bどちらでローンチ)
2) 判断材料:比較表1枚だけ(指標は最大3つ)
3) リスク&前提:やらない場合のコストも明記
4) ステークホルダー:誰が何をいつまで(責任分担の一行化)
5) 決裁:今日決める/保留なら“不足材料と締切”を宣言
2. 比べないことが教えてくれたもの
「全員が納得する案」を目指すほど、議題は増え、論点は拡散する。元社長の私が学んだのは、“最適”より“合意できる十分解”を早く選ぶこと。
そのために、比べる項目は3つまでに減らす。KPI、コスト、リスク——この3軸で良い。精度は実行で上げる。会議で完璧を作らない。
3. それでも前に進む理由(冒頭30秒/締め60秒の台本)
冒頭30秒(司会/責任者)
「この15分で決めるのは『A or B』です。判断材料はこの1枚、指標はKPI/コスト/リスクの3点のみ。
リスクは“やる/やらない”双方のコストで見ます。時間厳守で、保留の場合は不足材料と期日を必ず宣言します。」
締めの60秒
「結論はB案。理由はKPI到達確率と初期コストのバランス。
タスクは、プロト作成:田中(9/28)、法務確認:佐藤(9/30)。
リスク対応は“問い合わせ急増時の増員”を想定し、週次で監視。
不足が出たら10分スロットで即決裁。以上でこの議題はクローズします。」
まとめ
- 会議は“長さ”ではなく“決裁単位”で設計する
- 指標は3つ、資料は1枚、時間は15分で十分動く
- 保留は“不足材料+期日”をセットで宣言して次へ進む
次回予告
vol.61『資料はいらない日——“ホワイトボード15分”で合意を取った朝』
次回は、資料ゼロで合意形成を進めた実例。
図と短文だけで役員合意まで運んだ“ホワイトボード運用術”を公開します。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします


