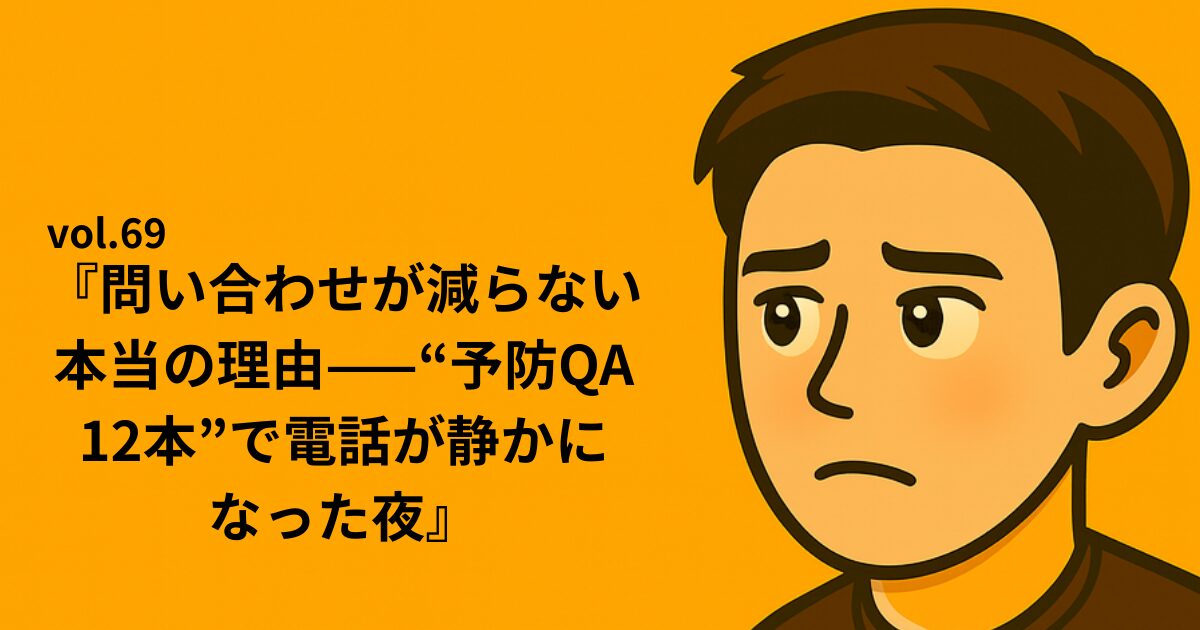⏱ 読了目安:約3分
“答える”より先に、“聞かれる前に置く”。
「また同じ質問だ。」——その夜、私は謝るのをやめて、12本のQAを置いた。
元社長として痛感したのは、クレームの多くが不具合ではなく不明確から生まれるということ。仕様変更・請求・納期・権限…電話の山の共通点は、“どこに答えがあるのか見えない”だった。
そこで作ったのが予防QA:12本だけ。検索される言葉順に、1問1答で“決め台詞”を示した。翌週、電話は静かになった。
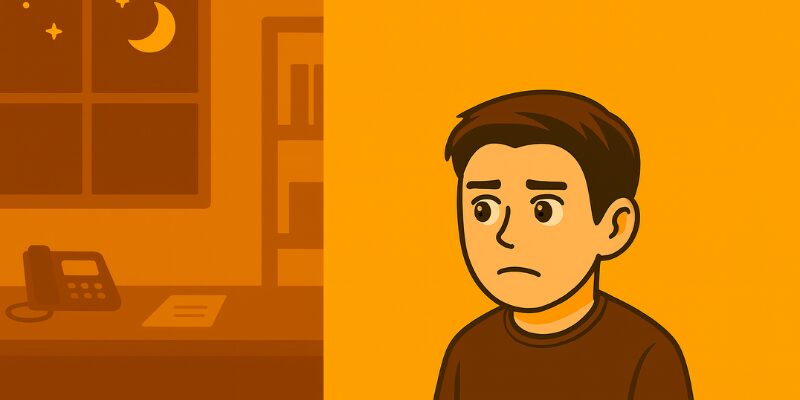
こんな人に読んでほしい
- 同じ質問が続き、現場が消耗している経営者・責任者
- FAQを増やすほど検索性が落ち、自己解決率が伸びないと感じる人
- サポートコストを下げつつ、満足度を落としたくないチーム
この記事で伝えたいこと
- “全部のFAQ”ではなく“予防QA12本”に絞るという視点
- 選定→執筆→配置の型(検索語から逆算/結論先頭/手順は3行)
- 明日から使えるタイトル・本文テンプレと配置パターン
1. 予防QAとの出会いで変わったこと
当時のFAQは100本超。なのに電話は減らない。原因は明確で、探すコスト > 電話するコストになっていた。
私は“頻出10件+炎上予防2件”の計12本だけに絞り、タイトルを検索語で始めた。
- 選定基準:①月間件数TOP10 ②炎上リスク高2(請求/障害時の連絡)
- タイトル:「請求 書き換え いつ」「権限 付与 できない」—検索語3語から
- 本文構成(1問1答・最大全角300字):
1行目=結論/2行目=理由(数字)/3行目=手順(最大3ステップ)/最後=連絡窓口
公開翌週、一次応答窓口の電話が前週比-38%。“場所”がわかれば、人は自分で解決する。
2. 比べないことが教えてくれたもの
他社の百科事典のようなヘルプセンターを真似るのをやめた。元社長の私が欲しかったのは、「今すぐの答え」だけ。
だから予防QAは“厚く書かない”。短い=冷たいではなく、短い=すぐ動けるだ。
- 検索語で始める:名詞3語(例:
請求 書き換え 締日) - 結論を先に:否定/肯定を1文で(例:
締日後の書き換えは不可です。) - 代替案を必ず:できない時は「次善」を提示(例:再発行/相殺)
3. それでも前に進む理由(テンプレ&配置パターン)
タイトル・本文テンプレ(コピペ可)
【タイトル】<検索語1> <検索語2> <検索語3>(例:請求 書き換え 締日)
【本文】
結論:◯◯は(可/不可/条件付き可)です。
理由:◯◯のため(法規/運用/システム制約)。過去12ヶ月の例外率は◯%。
手順:①◯◯を開く ②◯◯を選ぶ ③◯◯で保存(60秒)
連絡:解決しない場合は <窓口リンク>(平日9-18時)配置パターン(問い合わせの手前に置く)
- ① お問い合わせフォームの直前に「よくある12件」を横並び
- ② 検索窓は“オートサジェスト”で12件を最上位固定
- ③ 電話番号の横に「関連QA」のバッジを自動表示(3件まで)
まとめ
- FAQを増やすより、予防QAを12本だけ磨く
- 検索語で始め、結論→理由→手順→窓口の順で最短解決
- “問い合わせの手前”に置く。場所が答えの半分を決める
次回予告
vol.70『一次応答は15分以内——“既読だけでもOK”で満足度が跳ねた』
次回は、返答の中身より既読の速さを設計した話。一次応答の基準・テンプレ・運用(代行ライン含む)で、CS満足度がどう変わったかを公開します。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします