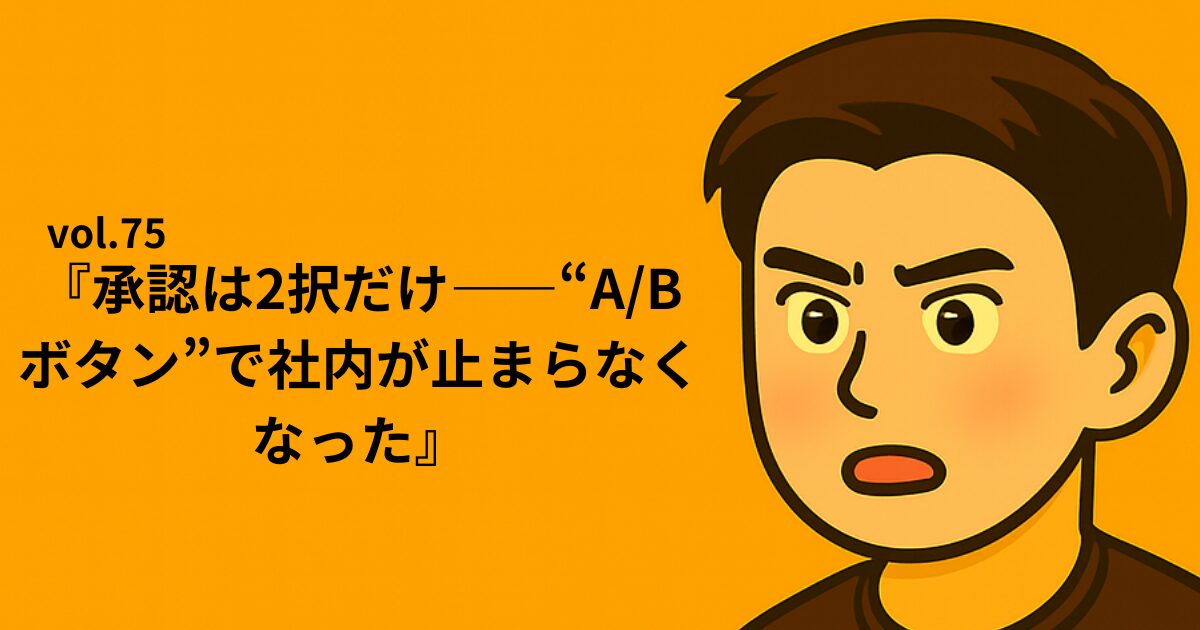⏱ 読了目安:約3分
決裁の迷いを“二択”に絞ったら、事業が前に進みはじめた。
「承認」か「差し戻し」。中間の選択肢をすべて消した。
元社長の私が痛感したのは、案件が止まる最大の理由は“無判断”だということ。
「保留」「あとで見る」「コメントだけ」を禁止し、A/Bの二択だけにした瞬間、責任の所在と期限が可視化された。判断をシンプルにするほど、会社は速く強くなる。——それがこの施策で得た答えだ。
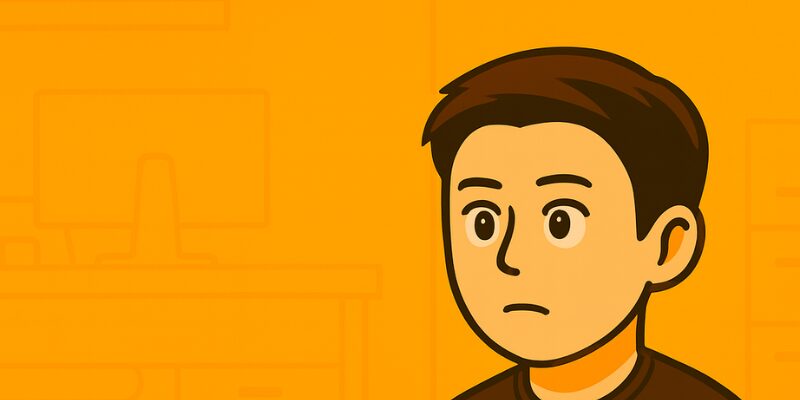
こんな人に読んでほしい
- 社内の承認待ちで案件や請求が止まりがちな人
- 「誰が止めているのか」が見えずに現場が疲弊していると感じる人
- 意思決定のスピードを上げたいが、どこから手を付けるか迷っている人
この記事で伝えたいこと
- “二択化”は迷いを減らし、責任と期限を明確にする最短ルールであること
- 判断材料を3行まで圧縮すれば、決裁は速くなり質も落ちないこと
- 止まっている時間こそ最大コスト——まずは可視化から始めること
1. “二択化”との出会いで変わったこと
ある月末、請求書発行が3日遅れ、キャッシュの着金もズレた。原因は「誰の承認待ちか分からない」が4カ所で同時発生していたからだ。
私は承認フローを全面的に見直し、画面上の選択肢を「承認」「差し戻し」の二択だけに設定。中間の「保留」「あとで見る」「コメントだけ」は禁止。判断材料は要旨・金額(または人時)・最大リスクの3行サマリーに統一、SLAは24時間以内にA/Bのどちらかを押す。押さなければ自動エスカレーション。
施策後、平均リードタイムは72時間 → 8時間に短縮。営業は見積から受注までの摩擦が減り、バックオフィスは「どこで何時間止まっているか」をリアルタイムに把握できるようになった。
二択は幼稚に見えるかもしれない。しかし実態は、意思決定コストを徹底的に削る設計だった。
2. 比べないことが教えてくれたもの
承認フローは会社ごとに“正解”が違う。他社の立派なワークフローと比べても、現場の速度は上がらない。私は自社の“詰まり”だけを見ると決めた。具体策は3つ。
①3行ルール:長文説明と資料の洪水をやめ、目的/金額or人時/最大リスクを3行で宣言。
②見える化:承認キューをカンバン化し、「誰が」「何を」「何時間」止めているかを全員に公開。
③差し戻しの型:差し戻す時は「不足情報テンプレ(何が・どれくらい・いつまで)」で返す。感情ではなく要件で戻す。
他社の“理想像”より、自社のボトルネックを一つずつ削る方が確実に速い。
3. それでも前に進む理由
二択化は最初こそ怖い。曖昧さという“保険”が消えるからだ。だが私は、判断ミスよりも「無判断」のコストの方が圧倒的に大きいことを嫌というほど味わった。
ミスは是正できるが、無判断は機会を消す。A/Bボタンは、チーム全員にその現実を共有するための装置だった。
まとめ
- 承認の“二択化”でスピードと責任が同時に生まれる
- 説明は3行、差し戻しはテンプレで——感情ではなく要件で回す
- 理想のフロー探しより、自社の詰まりの可視化と除去が最短
次回予告
vol.76『締切は“前倒し宣言”——デッドラインを味方にした日』
次回は、予定が守れないチームをどう立て直したか。前倒しを“宣言”に変えた具体策と、元社長が失敗から学んだ時間設計の話を書きます。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします