⏱ 読了目安:約3分
「前倒しで出します」と口にした瞬間、チームの時間がこちら側になった。
約束は守るものではなく、前倒しで奪い返すものだ。
元社長の私は、何度も締切に追われて燃え尽きた。原因は実力不足ではない。
「守れそうな期日」を静かに待つ文化だった。そこで私は、期日より先に「前倒し宣言」を公開するルールに変えた。宣言はプレッシャーではなく、味方だった。進捗が“見える”から、助けが集まり、品質も上がる。
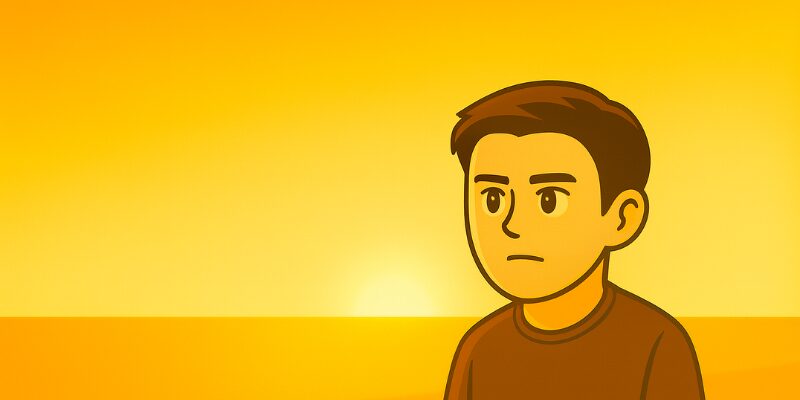
こんな人に読んでほしい
- 締切が近づくほど品質とメンタルが削られると感じている人
- チームの「いつ終わる?」が永遠に曖昧なままで疲れている人
- 日程遅延の言い訳ではなく、再現性のある時間設計を手に入れたい人
この記事で伝えたいこと
- “前倒し宣言”は進捗を集団戦に変える最短のスイッチであること
- 締切は守るより、設計して味方にする方がラクで強いこと
- 宣言→見える化→微修正の小サイクルで成果と信頼が同時に積み上がること
1. “前倒し宣言”との出会いで変わったこと
社長時代、私は「期日ちょうど」の提出が多い会社を率いていた。結果はお決まり——レビューの手戻りで納品が伸びる。
そこで方針を一行に絞った。「締切の48時間前に“前倒し提出版”を全員に見せる」。完璧でなくていい。未完成の8割版で構わない。代わりに、T-48で前倒し宣言+差分の箇条書きを添える。
これだけで変化は劇的だった。レビューの待ち行列が消え、意思決定は早まり、現場は夜を守れた。
仕組みはシンプルだ。
・T-72計画固め(要件・誰が・どこまで)
・T-48前倒し宣言(8割版+不足リスト)
・T-24磨き込み(指摘反映・数字詰め・表現統一)
・T-0 納品(差分と検収ポイントを先に提示)
「前倒し宣言」は、助けを呼ぶ合図でもある。声を出した人に、組織は自然と資源を寄せる。
2. 比べないことが教えてくれたもの
他社のプロジェクト管理術を真似ても、現場の癖は変わらない。私が学んだのは、自社の“遅延の型”にだけ効く仕組みを作ること。
そのために、次の3つを徹底した。
①成果の定義を先に出す:納品物の「OK条件」を箇条書きで公開。評価軸がズレて揉める時間をゼロに。
②バッファは黙って積まず、見せて積む:T-48の宣言自体が可視化されたバッファ。関係者の心理が締まる。
③バーンダウンを口頭で:毎日30秒、「残り3つ、今日2つ潰す、明日1つ」だけを共有。ツールより声で詰まりを出す。
比べないことで分かった。必要なのは万能ルールではなく、現場の摩擦を最小にする最小ルールだ。
3. それでも前に進む理由
前倒し宣言は、怖い。出した瞬間、できなかった言い訳が効かなくなるからだ。
それでも私が続けたのは、「守れた」より「早く出せた」ほうが信頼の増え方が大きいと気づいたから。
しかも、早く出すほど指摘が浅く分散し、品質は結果的に上がる。締切を味方にできた日、チームの空気は軽くなった。
まとめ
- 締切は“前倒し宣言”で集団戦に変えるとラクになる
- T-72計画固め → T-48宣言 → T-24磨き込み → T-0納品の小さな型で回す
- バッファは隠さず見せる——それが速度と信頼を同時に引き上げる
次回予告
vol.77『会議は“15分×砂時計”——雑談が消え、決まる会議に変わった』
次回は、だらだら会議をどう止めたか。砂時計方式・3スロット議事で、意思決定の密度を一気に上げた話を書きます。
おまけ・SNS連携
更新情報はX(旧Twitter)でも発信中!
@Okin_san_
元社長のリアル再出発ストーリーをお届けします


